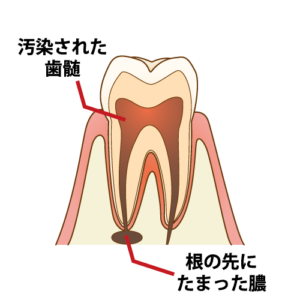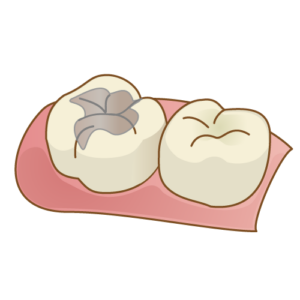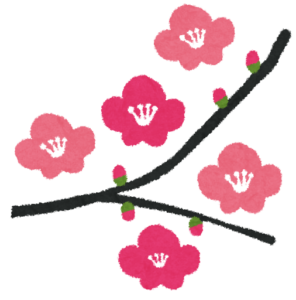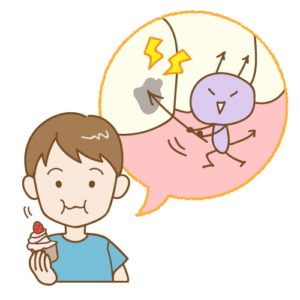こんにちは、清瀬いんどう歯科の町田です!(^^)!
以前、ブログで金属やお口の中のアレルギーについてお話致しましたよね🤗
今回は「ラテックス」アレルギーについてお話させていただきます❕
「ラテックス」とは一般的にゴムのことで、歯科治療とも密接な関係を持っています。
最も使用頻度が高いもので言うと、ゴム手袋(グローブ)が挙げられます。
ゴム手袋は、歯科治療において衛生面を保つために必ずと言っていいほど使用されています👐✨

ですがやはり、歯科治療で使うゴム手袋にアレルギー反応を起こす患者さんがたまにいらっしゃるそうです😱
当院ではまだラテックスアレルギーの方のご来院はまだありません。
ですが、ラテックスアレルギーの方のために、ラテックスフリーのニトリル素材のグローブの
ご用意がございます🌟
もし、ラテックスアレルギーをお持ちの方がご来院の場合は、事前にお伝えくださいね🤗🍀
ちなみに・・・
ラテックスアレルギーになりやすい方の特徴をご存知でしょうか❔
実は、日頃から天然ゴム製品を頻繁に身につける職業の方々が発症しやすいんです😲
医療関係、食品関係業、清掃業、製造業の職業の方や、医療処置を繰り返し実施している患者さん、
また、アトピー性皮膚炎や食物アレルギー(特にバナナ、アボガド、栗、キウイ)をお持ちの方は
発症のリスクが高いと言われています。
もちろん、医療関係の中には歯科関係職も含まれているので、自分自身も気を付けたいなあと
思うばかりです😌💭
もし日頃から天然ゴム製品使っている方で、症状や異変があった場合は速やかに
専門の病院に行かれることをオススメします🏥🚑
Instagram📱Twitter @kiyose_indo